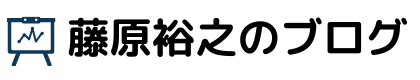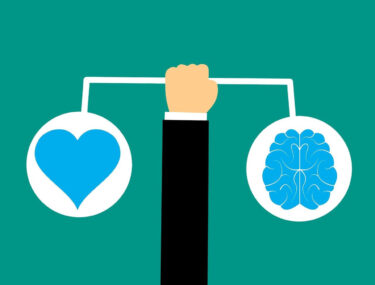【記事のポイント】
|
常態化するネット上の炎上
「思考」せず「反応」してしまう
今や当たり前のように毎日起きているのが「ネット上の炎上」です。
Twitterを開くとトレンドワードは目まぐるしく入れ替わり、その裏側で炎上は起きています。失言による炎上で世間から消えていく政治家や芸能人も珍しくありません。炎上発言の当時者が壊滅的な打撃を受けている中、大半の人は数日でその炎上ネタのことは忘れ、また別の炎上ネタで盛り上がっています。
私は失言をした政治家や芸能人を擁護するつもりはありません。しかし、
「次の日には忘れてしまうような炎上ネタが一人の人生を大きく狂わせてしまう」
このような事実に強い違和感を覚えます。そしてその違和感の正体をたどると、人々の「情報との向き合い方」「情報処理の仕方」に問題があることがわかります。
- 玉石混合のネット情報を疑うことなく受け入れてしまう(無思考)
- 情報を受けた瞬間の感情のまま脊髄反射的にリツイートや「いいね」を押してしまう(反応)
つまりネットの世界では多くの人が「思考ではなく反応」によって情報処理することで炎上という事態が引き起こされているのです。ネット情報に脊髄反射する今の人々に対し、 評論家の宇野常寛さんは以下のように問題提起しています。
タイムラインに流れてくる情報に対しほとんど脊髄反射的に反応して「発信」する人々は、あるいはニュースサイトが閲覧数目的で選ぶ扇情的な見出しに釣られてタイムラインの「空気を読み」、週に一度生贄として選ばれた目立ちすぎた人や失敗した人に石を投げつける人々は果たして「思考している」と言えるのだろうか。
宇野常寛「遅いインターネット」より抜粋
「思考社会」がやってくると期待していた自分
私はインターネットの出現によって皆が自分の考えを出し合う「思考社会」が実現すると期待していました。
- かつては一部の知識人しか手に入らなかったような情報が誰でも手に入る。
- その情報をもとに思考を巡らし自分の意見を発信する。
- しかもミレニアル世代を中心とする今の若い世代は、世間より「自分にとって大事なもの」を共有したがっている。
こうした私の期待は見事に打ち砕かれました。
宇野さんが指摘するように、現実はタイムラインに流れてくる膨大な情報に対し「自分に刺さる意見」を選択して自分の考えとして発信しているのです。そこにあるのは思考ではなく反射的に「反応」しているだけ。あるいは思考していても極めて浅い思考です。
私の考えはどこでどう間違ったのか。以下の点について考えてみたいと思います。
- 思考せず他者の意見に反応してしまうのはなぜか?
- ネットでの炎上と反応行動はどう関係しているのか?
- 反応を止めて思考モードに入るにはどうすればいいのか?
なぜ私たちは思考せず反応してしまうのか
どうして私たちはネット情報に対して脊髄反射的に反応してしまうのか。思考を阻害する要因をいくつか挙げてみたいと思います。
【要因1】人間は「思考が苦手な生き物」
一つ目は、人間とはそもそも「思考が苦手」「できれば思考したくない」生き物だからです。
身も蓋もない理由ですが、人間にとって「じっくり考えるという行為は自然な行為ではない」という点は押さえておく必要があります。思考したくないのが人の性(さが)。であれば、タイムラインに流れる膨大な他者の思考の波に乗って「いいね」しているほうが確かに楽です。人間にとって膨大な他者の思考の波に乗ることは処世術の一つなのかもしれません。
バイオ系ベンチャーを起業・運営する高橋祥子さんは自身の著書で以下のように語っています。
そもそも思考というのは、生物学的には多くのエネルギーを消費する行為です。したがって、思考しなくてもよい環境であれば生物は極力思考をしないことを無意識に選択します。
高橋祥子「ビジネスと人生の「見え方」が一変する生命科学思考」より抜粋
そう考えると、人々がタイムラインに「いいね」するのは「小難しく一人で考えるより皆と楽しさを共有するほうが集団生活の中で生存確率を高めるからという見方もできます。思考せず反応するのは身を守るために遺伝子に搭載された生存本能というわけです。
哲学者のハイデガーは日々の生活の中で世間に埋もれて主体性を失った状態のことを「ダスマン(世人)」と呼びました。タイムラインに「いいね」する姿はまさにダスマンです。
【要因2】考える隙を与えないネット情報の「速度」
普段は考えるのが面倒でも「さすがにこれは深く考えたほうがよさそうだ」という場面はあるでしょう。しかしそうした状況でも思考を阻害してしまのが2つ目の要因です。それは、
ネットの情報が速すぎることです。
ニュースサイトやSNSで流れる情報はあまりに膨大で速すぎるため、ニュース・投稿の一つ一つをじっくり読んで熟考する隙などありません。素早く「いいね」をしなければ膨大なタイムラインに埋もれてしまう。こうした状況では必然的に「反応」という形を取らざるを得ません。
ニュースサイトもじっくり読ませる記事よりキャッチ―なタイトルで分かりやすい記事を意識しています。読者に思考の隙を与えない方がYes-Noによる「反応」を引き出せますし、結果としてPV数を多く稼げるためです。今のネット社会は素早くYes-Noを表出させる装置になっており、それを助長しているのが速すぎる情報なのです。
【要因3】他者の「解釈」に支配される
ニーチェに、「事実なるものはない、ただ解釈だけがある」という有名な言葉があります。「情報=事実」と思われる人が多いかもしれませんが、ネットに流れる情報の多くは事実そのものではありません。評論家の岡田斗司夫さんはネットの情報について以下のような見解を述べています。
情報化社会の本質とは、「世界中の小さな事件の客観情報まで入ってくる社会」ではなく「大きな事件の解釈や感想が無限にあふれ出す社会」なのです。
岡田斗司夫「評価経済社会」より抜粋
高度情報化社会とは、情報の数が増えることではない。一つの情報に対する「解釈が無限に流通する」社会です。
つまりインターネットで流れる情報の大半は事実そのものではなく、事実に対する他者の「意見」や「解釈」のかたまりなのです。
他者の意見は事実そのものより私たちの心にすうっと入ってきます。フィルターバブルという言葉があるように、SNS上の他者の意見とは「自分と志向や価値観が同じ人の意見」です。心にすうっと入ってくるのは当然です。
そうなると事実から自分の解釈を導く前に他者の意見に心が支配されます。「この人の意見は共感できる」「この見方はちょっと違うかな」と選択モードに入ってしまうのです。選択モードはリツイートという行動につながります。リツイートは他者の意見に対する「賛同」の表明とも取れますが、実質は単に選択して反応しているだけともいえるのです。
私自身、タイムラインで次々と膨大な他者の意見を眺めているうちに自分の問題意識などどこかへ吹っ飛んでしまった経験が何度もあります。一度反応モードに入ってしまうとそこから抜け出すのはそう簡単ではありません。
どうしても反応してしまうなら新聞や雑誌を見ればいいのでは?との指摘もあるでしょう。しかしメディアも流している情報は事実に基づいた「意見」です。むしろメディアだからこそ価値判断が入ります。「事実のみ」を流すのではなく、その事実が良いことか悪いことか、なぜそんなことが起きたのか、どうすれば防げたのか、といった価値判断込みの情報を流すのがメディアの世界です。
7割の人の反応が「炎上」を引き起こす
- 人間は思考が苦手な生き物
- ネット情報は速すぎて思考する隙を与えない。
- 他者の「意見」に心を支配されて思考できない。
ネット情報にはこうした思考を阻害する要因が存在し、結果として生まれる現象が「炎上」です。
炎上はわずかな「火種」と「空気」によって起こります。ユダヤ教では人間関係を「1:2:7の法則」で説明します。これは周りに10人の人がいるとしたら、
- 1人は批判する人
- 2人は応援する人
- 7人はどちらでもない人
となり、幸せに生きるには「あなたを応援する2人と付き合えばよい」という教えです。ネットの世界に置き換えると、攻撃的な投稿で炎上の「火種」となる人は10人中1人、応援してくれる人は2人です。重要なのは残りの7人、「空気」のようにどっちつかずの人です。この7人が軽い気持ちで反射的に反応してしまうことで火が一気に燃え広がるのです。
7人それぞれが一呼吸置いて考えれば、何人かは応援に回る人もいるはず。多様な意見が形成されることで炎上は回避できるかもしれません。しかし反応を促す3つの要因が強すぎてそのよう姿にならない。そこが問題なのです。
反応せず「思考力」をアップさせる方法
私はネット情報に反応する人を一概に批判するつもりはありません。
- 様々な意見や価値観の中で、自分の気持ちにフィットする意見に共感を示す。
- 同じ価値観を持つコミュニティに参加する。
こうした行動はインターネットがなければ実現できなかったものであり、それで救われる人も少なくありません。面倒な思考などせず他者の意見に反応することで幸福に生きられるならそれはそれでいいでしょう。
しかし実際にはそうはなっていません。SNSやLINEに反応する毎日に生きづらさや虚しさを感じる人も少なくありません。
重要なのは反応と思考のバランスです。
「反応」はネット社会で生きる術として合理的な行動ですが、私はそれだけに依存するのは危険ではないかと感じます。ネット情報の7割は「反応」で処理するにしても、残りの3割は時間をかけて自身の内側と対話(思考)する必要があるのではないでしょうか。ではどうするか。
目新しいものではありませんが、私が「思考力」をアップさせるために効果的だと感じている3つの方法を紹介します。
【方法1】「デジタル断食」
一つ目の方法は誰もが思いつく「デジタル断食」です。
ネット社会の便益からあえて離れることで不便益を手に入れるというものです。
スマホを手放して「紙とペン」を持つ
デジタル断食するにはネット情報に接続するスマホをいったん手放す必要があります。「デジタルに覆われた日常」から離れるために「禅の日常」に触れる座禅体験ツアーなども話題になりました。
ただ座禅体験ツアーは頻繁に行けるものではありません。私が時々行っているのは「〇時以降はスマホに触らない」日を設けることです。どんなに興味深いニュースがあっても、仕事のメールが気になっても、その日の〇時以降はスマホの電源を切ってしまうのです。
スマホを手放す代わりに持つのが「紙とペン」です。
ある事実に対する自分の考えを紙に書き写す。書かれた文字は紛れもなく自分の内側から生まれたものです。その文字を読むと不思議と気持ちが落ち着いてくるのがわかります。私の場合、意味不明なことを書いていることのほうが多いのですが、それが今の自分を受け入れることにつながり、深い思考モードに入ることができるようです。
ここ数年、筆記具を購入する人が増えている理由の一つも「落ち着いて考えたい」と感じている人が多いからではないでしょうか。
「読書」をする
「読書」もデジタル断食の手段の一つです。読書の最大の利点は、
「情報に触れる速度を自分でコントロールできる」ことです。
消化できない速度で押し寄せる SNSのタイムラインと違い、本は自分の読解力と気分に応じて速度をコントロールできます。書かれてある内容(情報)は著者の「意見」ですが、SNSの投稿のようにその場で反応を求めたりしません。読書は著者の意見としっかり向き合うことができますので自然と「思考」につながります。
読書は自分に主導権がありますので、自分の問題意識や関心に合わせて読む本を選んだり、読み飛ばしながら必要な個所を探す自由もあります。
ちなみに私はタブレットで読書をすることが多いのですが、KindleではSNSやネット検索ができませんので、デジタル断食をしているのと同じ状態になります。
「リアル空間」に触れる
デジタル断食の3つめの手段はデジタルの反対側、すなわちリアル空間に触れることです。
ネット情報が他者の意見である限り、内容にいくら共感しても手触り感までは得られません。手触り感が得られない情報は翌日には次の情報に取って代わられる。そんな軽さを内包します。
手触り感を得たいとき、私はパソコンの電源を切って外に出るようにしています。
ある日、ネットスーパーや無人店舗の便利さを強調する記事を読み、もやもや感を覚えました。外に出て近所のスーパーに入ると、お客さんと店員が仲良く世間話をしている姿が目に飛び込んできました。「ここには無人店舗にはない価値がある」と、もやもや感の正体を知ると同時に、リアル店舗の価値について深く思考することができたのです。
【方法2】「一次情報」に触れる
思考モードに入る2つ目の手段は「一次情報」に触れることです。
一次情報とは意見や解釈が入らない情報の源流です。先のリアル空間も一次情報ですが、私が特に重視しているのは「統計」です。
ここで言う統計とは誰の意見も解釈も入らない純度の高い情報のことです。新聞や雑誌でも一次統計を取り上げたりしていますが、メディアが流すのは解釈の入った「記事」です。「第二四半期のGDPは〇%です」だけでは記事になりませんので、 「第二四半期のGDPは〇%に落ち込んだ。景気はまだ底打ちしたとは言えない。」といった解釈が加わります。解釈が加わった時点で一次情報としての純度は低下します。
思考モードに必要なのは解釈なしの情報ですので、私は統計情報をみるときは発表元に直接あたります。GDPの場合は内閣府のサイト、失業率の場合は総務省のサイトといった具合です。ただ発表元のサイトでも報告書は解釈が入っていることが多いので、なるべくExcelファイルになった数値を見ます。
先入観なしに統計をみると、その数値をどう解釈していいものか混乱することも多いですが、時系列でみたり、属性別にみたりするうちに点と点がつながったりします。時間はかかりますがそれが思考をしている証拠です。
【方法3】メディアサイトを選ぶ「スロージャーナリズム」
反応しづらいメディアサイトを選ぶことも重要です。
私が最近注目しているのが欧米で流行りつつある「スロージャーナリズム」です。現代のインターネットで量産されるYes-Noを迫る議論やフェイクニュースに対する反省として、時間をかけてでも正確で良質な情報発信を行う以下のようなネットメディアが勃興しています。
「デ・コレスポンデント(De Correspondent)」(オランダ)
「ディレイド・グラティフィケーション(Delayed Gratification)」(イギリス)
「プロ・パブリカ(ProPublica)」(アメリカ)
これらのメディアサイトで流れる情報は既存のニュースにコメントを加えるようなものではなく、時間をかけながらじっくり調査されたものです。専門的な記事が多いため、読書のような感覚でスローに読み進めることができます。じっくり思考モードに入れますので私は時々これらのサイトを訪れるようにしています。
まとめ
これまでみたように、インターネットの出現で期待された「誰もが自由に他者の意見に触れ、自分の考えを発信できる思考社会」はそう簡単に手に入るものではないようです。
Yes-Noを迫る拙速な議論やフェイクニュースがあふれ、自分の気持ちに合うか合わないかで良し悪しを判断し「いいね」という反応行為で発信する。結果としてあちこちで炎上が頻発しています。
どうやら私たちは思考力をアップさせるための努力を意識的にしなくてはいけないようです。
- スマホをいったん手放して「デジタル断食」する。
- 統計などの一次情報に触れる。
- 思考力を促す遅いメディアサイトにアクセスする。
こうした方法を意識的に取り入れながら反応と思考のバランスを取り戻す。「誰もが自由に他者の意見に触れ、自分の考えを発信できる思考社会」 はその先に見えてくるのではないでしょうか。