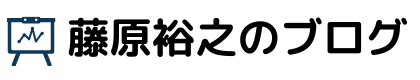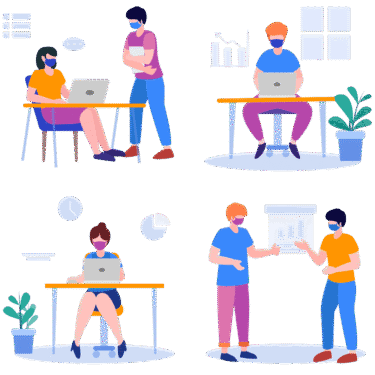上司よりAIに相談する若手社員
「上司や同僚よりAIに相談する若手社員が増えて困惑している」──私が地方で講演を行った際に会場から出た質問です。自社に生成AIを導入したら、社内の会話が減って風通しが悪くなって困っている、という訴えです。豊かな自然に囲まれた農村地域でこのような質問を受けるとは思いもよりませんでした。
電通の意識調査によると、週1 回以上「対話型AI」を使用している人は全体で2割程度。これに対し、10代は4割以上、20代は3割以上と若者ほどAIの使用頻度が高いという結果が出ています。若者のAI使用が多いのは納得ですが、衝撃的なのは利用目的です。「相談に乗ってほしい」「話し相手になってほしい」など、以前なら家族や友人に求めていたようなことが上位に並んでいます。なるほど今の若者世代にとって、上司や同僚よりAIに相談するほうが自然なのです。
ChatGPTに代表される対話型AIの登場により、生成AIは誰もが利用できる一般的なビジネスツールになりつつあります。コロナ禍を経て対面コミュニケーションの重要性が再認識されてるところ。しかし社員が職場に戻っても、仕事の相談は生成AI、部内のやり取りはチャットというのでは在宅勤務と何ら変わりません。
「現実そのもの」から遠ざかる現代人
上司や同僚よりAIと話したがる若手社員──この現象の意味するところは「現実そのもの」から遠ざかる現代人の姿です。広告やメディア・SNSなど、社会システムを通じて認識する「現実」というものは、「ノイズ」を切り落とした後の情報で作られたものです。
現代人にとって「現実そのもの」は面倒で煩わしい。だからそうしたノイズを切り落とし、「見たいもの」「知りたいもの」「気持ちよくしてくれるもの」を提供するAIのほうが、生身の人間よりありがたい存在となるのです。「バカの壁」で知られる養老先生は、ビッグデータを分析するAIが「現実」を作り出していると、現実そのものから目を背けようとしている現代人の姿に警鐘を鳴らしています。
いつから「統計」が「現実」になってしまったのかという問題ですよ。「統計」を「データ」と言ってもいいけど、今や、ビッグデータを分析するAIが「現実」を作り出している。
養老孟司「 AI支配でヒトは死ぬ」より
非言語情報が「ノイズ」扱いされる
AIは膨大なデータセットとディープラーニング技術を用い、情報収集・整理から報告書の作成、文章校正・翻訳、企画提案、質疑応答まで、圧倒的なパワーとスピードでこなします。生成AIが提供するのは専ら「言語情報」です。
一方、生身の人間と対話するとき、言語はコミュニケーションの一部に過ぎません。言語化が難しい感情や表情、身振り手振り、声のトーン、共感など「非言語情報」でのやり取りが多くなります。「来た球をパッと打つ」の名セリフを残した故長嶋茂雄さんの経験知は非言語情報そのものです。プロジェクト立ち上げ時など、思いや感情を共有化したいときは対面でなければうまくいかないのは誰もが経験するところです。
心理学者アルバート・メラビアンの研究によると、コミュニケーションにおける言語情報の影響はわずか7%、残り55%は視覚情報、38%は聴覚情報です。言語情報を燃料とする生成AIだけではコミュニケーション手段の1割しか活用していないことになります。最適なコミュニケーションとは、言語情報と非言語情報の両方を最適な場面で使用することです。
つまり、生身の人間との対話を避けてAIと仲良くする若手社員は、コミュニケーションの9割を担う非言語情報を「ノイズ」扱いしていることになるのです。
AI利用は「ほどほど」に
ビジネスパーソンなら非言語情報が重要であることは理解しています。問題は頭では理解しているつもりでも、生成AIを使い始めるとそうならない──意識と行動の不一致にあります。筆者もしばしば経験することですが、生成AIで作業すると瞬時に理路整然としたアウトプットが出てくるため、それだけで仕事が終わったような錯覚に陥ることがあります。特にコスパ意識の高い若い社員がこうした錯覚に陥るのはよくわかります。
では生成AIの圧倒的なパワーとスピードに巻き込まれないようにするにはどうすればいいのでしょう。筆者が心がけているのは、生成AIが有効なタスクと対面のやり取りが有効なタスクを事前にイメージしておくことです。例えば商品の企画提案を行うときのプロセスは、必要な情報を収集・整理(①)、アイデアのたたき台を出す(②)、チームメンバーでアイデアを具体化(③)となります。
情報収集・整理は生成AIがいとも簡単にこなしてくれます。問題は②のプロセスです。担当者が対話型AIとの壁打ちにのめり込みすぎると、たたき台のレベルを超えて具体的な商品イメージまで達してしまうことがあります。AIが生み出す商品イメージが素晴らしいものであれば、担当者はチームメンバーの意見を聞く必要性を感じられなくなり、③のプロセスをスキップしようとするかもしれません。こうした事態にならないよう、事前に一連の作業プロセスをイメージしておくことで、生成AIとの壁打ちを「ほどほど」にとどめておくことができます。
競争力の源泉は非言語情報
社員の経験知(非言語情報)が入っていない企業の商品は競争力を失います。生成AIに投入される膨大な言語情報はライバル社でもリーチできます。ライバル社が同じ生成AIを使って壁打ちすれば、同じような商品が生まれる可能性が高まるでしょう。しかし社員同士の対面コミュニケーションから生まれる非言語情報にはライバル社でもリーチできません。非言語情報から生まれる商品は高い競争力を持つのです。
ハンナアーレントは人間の営みを「労働」「仕事」「活動」に分け、もっとも価値が高いのは「活動」と主張しました。「活動」とは人間同士が対話を通じて協力しあう非言語情報の営みです。生成AIの時代になっても、競争力の源泉は対面コミュニケーションから生まれる非言語情報にあることを忘れてはいけません。